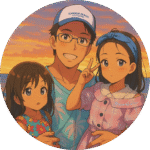 かける
かけるこんにちは、かけるです。
医療系企業でフルタイム勤務しながら2人の娘を育てるシングルファザーです。
育児も仕事も全力で取り組んでいるからこそ、子供の「放課後の過ごし方」は、我が家にとって非常に重要なテーマです。
わが家では、長女の小学校入学を機に、公立学童と民間学童の両方を併用してきました。実際に使ってみてわかったそれぞれのメリット・デメリットや、学童選びで後悔しないためのポイントを、体験談ベースでお伝えします。
「どっちがいいの?」「どう選べば後悔しない?」と悩んでいる方のヒントになれば嬉しいです。
公立学童と民間学童の基本的な違い
| 種類 | 特徴 |
| 公立学童(放課後児童クラブ等) | 自治体運営。学校の敷地内にあることが多く、費用は安価。基本は自由時間。 |
| 民間学童 | 民間企業が運営。教育や体験プログラムが充実しているが、費用は高め。 |
公立学童を使って感じたこと
✅ メリット①|学校内の安心感
学校内や隣接施設で運営されているため、子どもたちにとって環境の変化が少なく、リラックスして通えます。「学校の延長」のような感覚で、慣れるまでが早い印象でした。
小学校入学・妻の死など長女にとって環境が一気に大きく変化したため、わが家にとってこの点はとても大切でした。
✅ メリット②|費用がとてもリーズナブル
自治体によって異なりますが、わが家の場合は月額6,000円ほど。費用を抑えつつ、放課後の居場所を確保したい家庭にはありがたい制度です。
また、ひとり親や低所得世帯には費用免除の制度がある自治体もあります。
❌ デメリット①|習い事・体験の要素は少ない
スタッフの数に対して子どもの人数が多く、基本的に自由遊び。宿題タイムはあるものの、フォローまでは難しい印象です。「放課後も学びの時間にしたい」という家庭には、物足りなさがあるかもしれません。
ただ、わが家のように、放課後に友達と遊ぶ時間を取りにくい家庭にとっては、友達と自由に遊べる貴重な時間となっているとも感じます。
民間学童を使って感じたこと
✅ メリット①|体験活動がとにかく豊富
私が選んだ民間学童では、平日だけでなく土日にも体験活動が豊富でした。
田植え、磯遊び、料理、ものづくり、サマーキャンプ…。
季節やテーマに応じたアクティビティに連れて行ってくれて、「今日はこんなことしたよ!」と報告してくれる子どもの様子に、親としての喜びも大きかったです。
逆に「これはあんまり好きじゃなかった」など、子どもに合わないことや、まだ早いことを知るきっかけにもなっています。
✅ メリット②|習い事を兼ねられる
プログラミング、英語、ダンス、書道、球技など、多彩なプログラムが用意されていて、「学童時間内に習い事まで完結する」のはとても助かる!
ひとり親や共働き世帯など、放課後の送迎が難しい家庭でも、やりたいことをやらせてあげられるため、親も気兼ねなく仕事に集中できます。
わが家では運動系のプログラムをメインに選びましたが、送迎の負担がゼロになることで、帰宅後の時間に余裕も生まれました。
また、選択したプログラムが合わなかったときに、すぐに他のものに変えやすいのもとても魅力。わが家は、プログラミングを少しやってみましたが、2か月でやめて他のプログラムに変更しました。
✅ メリット③|柔軟な対応で、働く親の味方に
わが家が通っている民間学童は、夜10時まで延長可能なため、急な残業や予定変更にも安心して対応できます。
実際にはそこまで遅く預けたことはありませんが、**「いざとなったらお願いできる」**という安心感があることで、日中の仕事により集中できると感じています。
また、習い事や自宅への送迎サービスがある点も大きな助けになっています。基本はお願いせず自分でやっていますが、「お願いできる選択肢がある」という安心感があります。
❌ デメリット①|費用は高い
我が家は、週2回の利用+プログラム参加+月1回程度週末イベント参加で、月額7~8万円ほど。子どもの成長にはとても有益だと感じていますが、正直、家計にとっては悩ましい部分です。
❌ デメリット②|人見知りの子には合わないことも
民間学童には、さまざまな学校・学年の子どもたちが集まってきます。
うちの子も最初は「知らない子ばかりで安心できない」と言い、慣れるまで少し時間がかかりました。
性格によっては慎重に考える必要があると思います。
我が家の選択|両方を組み合わせたハイブリッド型
最終的に、我が家では「公立学童+民間学童(週2回)」の併用に落ち着きました。
- 公立学童 → 放課後の居場所、低コストで日常の安心感
- 民間学童 → 教育・体験・習い事を兼ねた成長機会
1つに絞らず、必要に応じて組み合わせることで、費用と満足度のバランスを取りやすくなります。
使い分けのコツ|家庭のリズムと子どもの個性に合わせて調整
学童選びで私が最も重視したのは、**「わが家の生活との相性」**です。
ひとり親の私にとっては、以下のような点が判断の軸になりました。
- 子どもたちの幅広い興味に、どうやって応えていくか
- 他の習い事や仕事の都合などに対して、学童をどのように生活に組み込めるか
- 学童以外の出費とのバランスはどうとるか
民間学童に関しては、子ども自身との相性がとても大切だと感じたため、いくつかの施設に実際に足を運びました。
スタッフの雰囲気や安全面、施設の環境なども確認した上で、子ども自身に選んでもらうことも大切にしました。
また、入学後も「週何回通うか」「どの曜日にするか」「どのプログラムに参加するか」など、状況に応じて柔軟に見直すことを繰り返してきました。
わが家では現在、平日は公立学童をメインにしつつ、週2回ほど民間学童を活用するスタイルに落ち着いています。
家庭の状況や子どもの気持ちは変化するものだからこそ、「一度決めたら終わり」ではなく、家族に合った形を都度模索していく姿勢が大切だと感じています。
まとめ|「どっちがいいか」より「どう使いこなすか」
公立と民間、それぞれに良さと課題があります。
大切なのは、料金や内容の比較だけでなく、**「わが家の暮らしと価値観に合うか」**という視点。
- 時間の余裕がないからこそ、放課後を“ただの預け先”にしない
- 子どもの性格と親の働き方をよく考える
- 柔軟に使い分ける
そんな姿勢が、結果的に後悔しない学童選びにつながると実感しています。
子どもの“今”を守りながら、“未来の力”も育ててくれる――。
そんな放課後の過ごし方を、これからも柔軟に模索していこうと思います。
▶ 関連記事リンク(内部リンク)
- → 【忙しい親の味方】学童でもできる習い事の選び方
- → 【平日ワンオペのリアル】シングルファザーの1日ルーティンと時間管理術


コメント